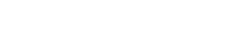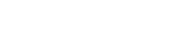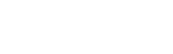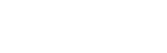私はクラシック音楽ファンなので、本屋さんでその方面の本があればあまり考えずに買うことがあります。「西洋音楽史」も軽い気持ちで購入しましたが、一気に読んでしまいました。レコードでもCDでも聞き終わった後、大変気に入ったらもう一度最初から聴くことがあります。それと同じでこの本ももう一度最初から読みました。名著だと私は勝手に思っております。各章ごとの私の感想などここに書いても意味はありませんので、私なりの”著者の想い”を抜粋させていただくという形で紹介します。
第1章 謎めいた中世音楽 初めに”グレゴリオ聖歌(グレゴリアン・チャント)”ありき・・まあ、こうゆう始まりはよくあるパターンです。私は”グレゴリオ聖歌”のレコード、CDは一応所有しておりますが、ほんの数枚という程度です。正直、長時間聴くのはなかなかつらいものがあります。グレゴリオ聖歌は楽譜によって組み立てられた音楽ではなく、民謡のように口頭伝承されるという点で厳密には”音楽”ではない等々・・また西洋世界の成立と”音楽”との関係性など著者の幅広い視点を感じます。
第2章 ルネサンスと「音楽」の始まり この章の中で非常にスリリングな感想を持った箇所を一部抜粋させていただきます。イギリスとフランスの間で戦われた「百年戦争」によってイギリスの音楽が大量にフランスに流れてきて、この時代のイギリスの音楽が中世フランスの音楽に多大な影響を与えたとのことです。「イギリスの音楽が温かく響くのは、中世フランスでは用いられなかった3度の音程を使用するからである。どことなく”グリーンスリーブスを連想させ、ほとんどザ・ビートルズのように響く部分があるのが不思議だ。」ザ・ビートルズが登場するこの部分は非常に興奮しながら読んだ箇所です。
第3章 バロック 既視感と違和感 いよいよバロック音楽についてです。絶対王政の音楽、プロテスタント・ドイツの音楽文化ときてバッハが登場します。バッハについて著者の私見を少し長くなりますが抜粋させていただきます。「バッハの音楽を作曲技法的かつ歴史的に理解する難しさを考える時、”音楽の父バッハ”とか”バッハの平均律クラヴィーアは音楽の旧約聖書”といった決まり文句でもって彼を神格化することに対して、つい距離をとりたくなってしまうというのが、私の本音である。バッハ神話を真に受ける代わりに、私は思わずそれを歴史的な文脈に置いて相対化したくなってしまうのだ。周知のように、死後半世紀近くあまり顧みられなかったバッハは、1829年のメンデルスゾーンによる『マタイ受難曲』の100年ぶりの再演とともに劇的な復活を遂げ、19世紀ドイツにおいて”音楽の父”へと神格化されるに至った。しかしながら19世紀のこのバッハ熱の背後には、多分に政治的背景(プロテスタント・ドイツ・ナショナリズムとでもいうべきもの)があっただろうことを決して忘れてはならないと思うのである。」私にとって、この本の一番のハイライト部分というか核心の箇所です。
第4章 ウィーン古典派と啓蒙のユートピア 人気の作曲家、モーツァルトやベートーヴェンあたりが登場します。
第5章 ロマン派音楽の偉大さと矛盾 19世紀に活躍した大作曲家たち、シューベルト/シューマン/ショパン/リスト/ワーグナー/ブラームス/ドヴォルザーク/チャイコフスキーなど・・・”個性”の百花撩乱についての考察とか鉄骨フレーム構造になり巨大化したピアノの話、グランドオペラについてなどなど・・現代に通じる大変興味ある史実を知ることが出来ます。
第6章 爛熟と崩壊 西洋音楽史の最後の輝きか?ポスト・ワーグナーの時代、リヒャルト・シュトラウスと巨大オーケストラ、神なき時代の宗教音楽か?マーラーの交響曲など・・・
第7章 20世紀になにが起きたのか? 第一次世界大戦(ヨーロッパ大戦?)が音楽に与えた影響についての考察、ストラヴィンスキーが自身のパロディ技法を駆使した”プルチネルラ”、現代音楽に通じるシェーンベルクの”12音技法”とか、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーンなどモダン・ジャズについてなどなど興味はつきません。

 0
0