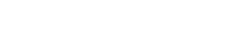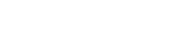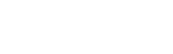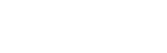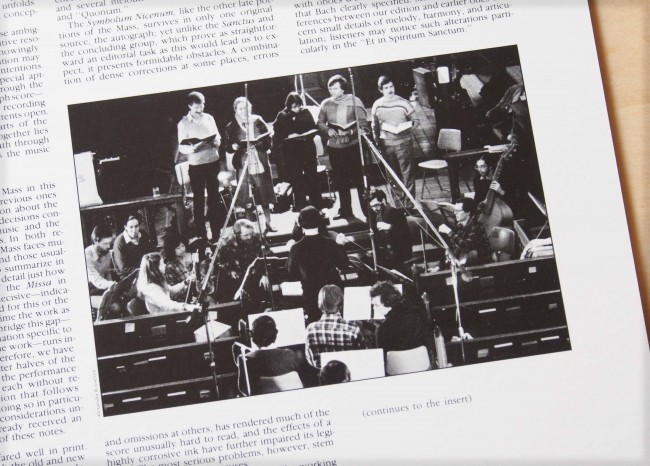「J.C.バッハの”ミサ曲ロ短調”は、ベートーヴェンの”ミサ・ソレムニス”と並んで、規模の大きさ、音楽的密度の高さから、ミサ曲の歴史に於ける頂点のひとつといっても過言ではない」と言われています。古くはカール・リヒター指揮、あるいはオイゲン・ヨッフム指揮、オットー・クレンペラー指揮の演奏等・・・共通するのは大人数の合唱団、管弦楽団による重厚で荘厳な”ミサ曲ロ短調”です。
アメリカ合衆国のバッハ研究者であるジョシュア・リフキン指揮、バッハ・アンサンブル(オリジナル楽器使用、20人編成)の”ミサ曲ロ短調”では各声部一人ずつしか当てられていません。よって、室内楽をバックに各ソリスト達が歌う”キリエ”、”グローリア”など、まさに天上の音楽を聴いているようなイメージです。なんだか軽い、パッとしないと思われる方もいらっしゃるでしょうが一度聴いてみてください。一人で歌うのですから、歌い手の力量が大きく影響しますから歌い手の緊張感は半端ではありません。がしかし、ソプラノのジュディス・ネルソン、ジュリアン・ベアドも大変素晴らしい歌唱で応えています。
”ミサ曲ロ短調”については、プロテスタント(ルター派)のバッハがどうしてカソリックのミサ典礼全体に曲をつけようとしたのか、あるいは完成までに多大な時間を要したかなど謎の多いことでも有名です。ラテン語の典礼文に沿ったミサ曲をバッハがキリスト教の普遍的な意味合いを自身の音楽にのせ、カソリック、プロテスタントの枠を越えることにあったというのが定説になっているみたいです。実際、カソリックとプロテスタントの対立から戦争が起きていた時代であったことは歴史の教科書に載っています。ドイツ語ではなく、ラテン語のよる典礼によってバッハは広義な意味で将来を見据えた宗教音楽の総合体を目指したということでしょうか?
ジョシュア・リフキン指揮、バッハ・アンサンブル”ミサ曲ロ短調”のLPレコードは、1983年度の英国グラムフォン誌レコード賞を受賞しています。また、音質も非常に優れています。冒頭の「キリエ(哀れみの讃歌)」の中の「キリストよ、憐れみたまえ」のソプラノとアルトの二重唱、「グローリア(栄光の讃歌)」の中の「いと高きところには神に栄光あらんことを」の合唱の素晴らしさは、なにか一歩を踏み出す勇気をもらえる感じがします。機会があれば一度聴かれることをお薦めします。CDが発売されているかどうかはわかりません。廃盤であればヤフオクでゲットできるかどうか・・・

 0
0